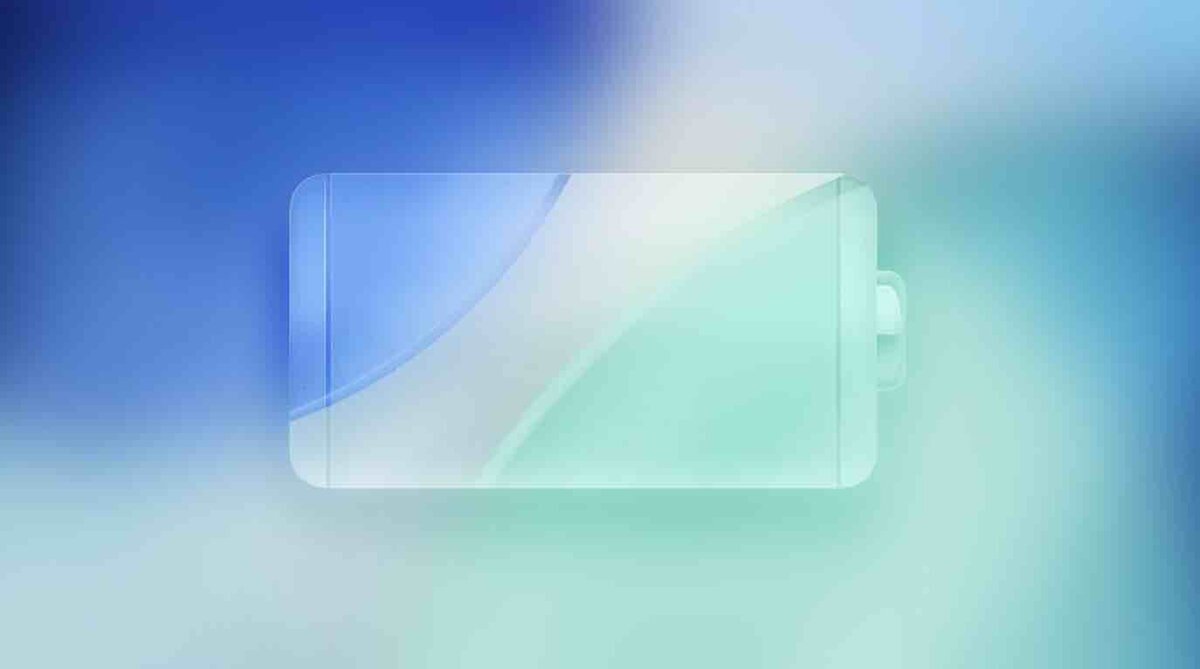
✅ この記事では、「iPhone 16 Pro Maxを1年間80%充電制限で使い続けたユーザーの検証結果」を紹介し、バッテリー寿命への影響や日常使いの快適さについて解説します。
どうも、となりです。
iPhone 15シリーズから追加された「充電上限80%」の設定。バッテリーを長持ちさせたい人にとって気になる機能ですが、本当に効果があるのかどうかはまだ議論が分かれるところですよね。今回紹介するのは、海外ユーザーがiPhone 16 Pro Maxで1年間この機能をオンにし続けた実体験。そこから見えてきたのは、「思ったより差が出なかったかも…?」という意外な結果でした。
この記事を読むと、80%制限を使うべきかどうか、そして日本ユーザーにとってのメリットとデメリットがイメージできるはずです。
80%充電制限で1年使った結果
検証したユーザーは、2024年9月からずっと「充電上限80%」を維持。ズルはせず、フル充電はiOS側のキャリブレーションで自動的に行われるときだけでした。
その結果、1年後のバッテリー最大容量は94%。充電サイクルは299回。比較対象として、同じ時期に制限なしで使っていた同僚の16 Pro Maxは96%/308回だったそうです。つまり、差はわずか2%程度。
まとめると、「80%制限をしてもしなくても、1年間での劣化スピードは大きく変わらなかった」と言えるわけです。
iPhone 15の時も同じ傾向?
実はこのユーザー、前年のiPhone 15 Pro Maxでも同じ実験をしていました。そのときの1年後の最大容量は94%。今回の16 Pro Maxとほぼ同じ結果になったんです。
さらに2年目を迎えたiPhone 15 Pro Maxは88%/352回にまで低下。これを考えると、80%制限の効果が出るのは「数年スパン」で見て初めて差がつくのかもしれません。
要するに、1年単位では目に見える差はほとんどない、ということですね。
なぜ1年だけだと効果が見えにくいのか
ここで気になるのが、「どうして80%制限をしても1年では差が出なかったのか?」という点です。理由はいくつか考えられます。
まず、リチウムイオン電池には初期劣化と呼ばれる段階があり、使い始めの1年ほどはどんな使い方をしても容量がある程度落ちてしまうんです。このため、80%に制限しても効果が数字に表れにくいんですね。
次に、バッテリーの劣化要因として大きいのは「充電サイクルの回数」と「高電圧の状態に長時間置かれること」。80%制限はこの“高電圧ストレス”を減らすのに有効ですが、1年・約300回程度の充放電では影響がまだ小さく、差が埋もれてしまいます。
さらに、実験者も指摘していたように、発熱要因(特にMagSafe充電の熱)が1年目は強く効いてしまうため、上限制御のメリットが薄れてしまう可能性もあります。
まとめると、「80%制限の効果はすぐに見えるものではなく、2〜3年と長期的に積み重なったときに差として表れてくる」ということなんです。
使っていて不便はなかった?
もちろん、常に80%で止めるのは快適とは限りません。ユーザーは「外出先でカメラやGPSを多用するとバッテリーが不安になる」とコメントしています。
ときどきiPhoneがフル充電を実行してくれるので助かることもありましたが、「せめて90〜95%まで充電できたほうが現実的かもしれない」とも語っていました。
ここからわかるのは、「長寿命か快適さか」のトレードオフをどう受け入れるか、という点です。
日本ユーザーにとっての意味
日本のユーザーは特にiPhoneを長く使う傾向があります。2〜3年使う前提なら、80%制限の効果が少しずつ効いてくる可能性はあります。
ただ、毎日の通勤・旅行・カメラ利用が多い人にとって、20%分のバッファがないのは大きな不安材料。モバイルバッテリーや急速充電器を持ち歩くかどうかで、実用性の評価は分かれるでしょう。
関連して、バッテリー寿命に直結する充電習慣をまとめた記事もあるので、あわせてどうぞ: iOS 26バッテリー機能の進化|アプリ異常消費を検出して節電に役立つ
今後の見通し
ユーザーはすでにiPhone 17 Pro Maxに乗り換え、同じ80%制限で次の1年を試すとのこと。大型バッテリーや素材変更(アルミ採用)の影響も検証されるようです。
Appleとしても、バッテリー寿命を延ばす方向性は継続するとみられるので、今後は「80%だけでなく柔軟な上限設定」などの機能拡張が期待されます。
まとめ
iPhone 16 Pro Maxでの1年検証では、80%充電制限によるバッテリー劣化防止効果は「ほぼ誤差レベル」でした。とはいえ、2年以上使う場合には小さな差が積み重なる可能性があります。
日常の不便さを許容できるなら選ぶ価値はあり、そうでなければ90〜95%制限が現実的かもしれません。みなさんはどう思いますか?
ではまた!
